大容量モバイルバッテリー MP-16000レポート2
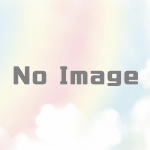
先日購入しました大容量モバイルバッテリーの MP-16000ですが、1回目の満充電が終わりましたので、この時点での能力を測ってみました。
対象はおなじみのNEC LavieZ PC-LZ550HSです。こちらをIntelBur ...
クルマdeチャージャー2 CARCHA03購入&分解&レポート

先日予告しておりました、サンコーレアモノショップの「クルマdeチャージャー2 CARCHA03」の方が届きましたので、簡単にレポートしたいと思います。
パッケージはこんな感じ。
まぁいろんなタイプがあるうちの一つと ...
大容量モバイルバッテリー MP-16000購入&分解&レポート

注文していた大容量モバイルバッテリー MP-16000が届きました。
価格は5980円(送料込)やっすい!!
これ、DC5V単体出力じゃないんですよね。DC19V出力まで可能なマルチモバイルバッテリーで最大60W出力。 ...
ノートPCを充電することの出来るモバイル大容量バッテリー考察2

>先日この大容量バッテリー考察の方を行いましたが、更なる情報の追加を行いました。1円あたりの容量も入れて欲しいとの意見があったので一応は追加してありますが、あくまでも目安程度で実際に役に立つ情報になるかは微妙かも。
結局 ...
車のシガーソケットからAC100Vに変換するインバータの仕様を調べる

車のシガーソケット(DC12V/24V)からAC100Vへ変換するインバータ、ホームセンターやカーショップで良く売っているのを見かけるとおもいます。これを使えば、家庭用AC電源で動作するものがひと通りは車の中で使えるようになるという便 ...